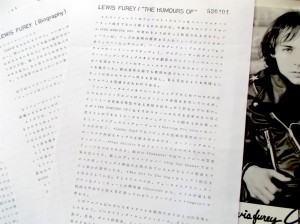師走を迎えたにもかかわらず一向に忙しくないのもどうかと思うがやはり、というか今年は何もしなかった。身辺整理よろしく持ち物を処分したりは継続しているが新たに補充されるモノの方が多かったりで全く身軽にならない。
そんなわけで新たな一冊、橘川幸夫氏の「ロッキング・オンの時代」を読んだ。72年のROの立ち上げからの約10年の記録。僕がROを読んでいたのは中学から高校の途中までの数年で、最初に買った時(中学生だった)はまだ10号にも満たず、定価¥180ぐらいでペラペラのミニコミ誌のようだった。内容的には今考えると60年代末から70年代初頭の雰囲気を残した、僕らより一世代上の、ロックと思想を結びつけるというかロックを思想として捉える論評が大半を占めていた。そういった傾向は当時(72〜3年)のロック・ジャーナリズム一般にもまだ残っていたけれどNMM(ニューミュージック・マガジン、今のミュージック・マガジン)が総体や現象としてロックを捉えていたのとは対照的にROは作品と個人(リスナー)の共同幻想(と言っていいかどうかは判らないが)に立脚していたように見えた。
雑誌の中核だった渋谷、岩谷、松村、橘川各氏の文章はそれまで読んでいたNMM、MLや音楽専科とは違い、やや(いや、かなりか)観念的すぎるきらいもあったがそこが当時は魅力的だったし何より4人の文体が独特で、全く重なることなくそれぞれ孤立していたのが特徴的だった。他誌では酷評されていた初期のドイツロックなどにも全く別の角度から新たな評価を与えていたし大類信によるデザインの表紙も書店では異彩を放っていた。岩谷・松村らが製作したイターナウの自主カセット(千野秀一も参加していた)も買って、彼らがなぜだかNHKの若者向けテレビ番組(「高校中退」とかのテーマだったような)に登場し1曲演奏したのも観ている。(余談だが件の自主カセットについていたポスター(無地のグラデーション)が同時期に中野レコードが作ったKaruna KhyalのLPに付属していたポスターと同じだった記憶がある。どちらも手元にはないので確認できないが、もしそうだとしたら何か関係があったのだろうか)
だが高校に入ったぐらいでパンクが勃興し、創刊号から読んでいたロックマガジン(初期数冊はROの影響が見え隠れしていた)が76年にニューヨークとロンドンでまだアンダーグラウンドだった初期パンクムーブメントを取材して誌面も一新した頃、惰性で買うようになっていたROで「パンクって要するに理由なき反抗でしょ」みたいな記事を読み、程なくして購読をやめた。大量にあったバックナンバーは大学の頃にまとめて処分してしまったのだが実家に初期の号が数冊残っていた。3号の表紙は真崎・守+宮西計三とあるので後に有名になる宮西氏がアシスタントをしていた時期のものだろう。ご存知の通り宮西氏は80年前後に三流劇画ブームで浮上し、宮西計三バンドを結成、WH結成前の栗原と松谷がギターとドラムスで参加していた。ちなみにその当時のバンド・マネージャーはエロ劇画雑誌編集長で初期フールズメイトでドイツロックやオカルティズムの記事を集中的に執筆しアシュラ山本の異名をとったやまもっちゃんこと山本雅幸氏。やまもっちゃんを媒介として栗原はその後、北村昌士のYBO2結成に関わることになる、というのは内輪の話。
閑話休題。というわけで近年までROがまだ存在する、まして邦楽ロック専門誌にも枝分かれしてそちらの方が業界で影響力がある、などということもほとんど知らなかった。興味がなくなる、というのはそういうことで本屋の一番目立つところに置いてあってもまったく目に入らなかったのだろう。いずれにしろこの「ロッキング・オンの時代」に書かれている40数年前(ロックとは洋楽だった時代だ)とはロックの意味性もそれを取り巻く世界もまったく変容してしまった。
しかしSNSやネットでタダで入手出来る情報(それも不確かな)よりも、こういう当事者の証言がまとまって一冊になったものの方がはるかに面白いし対価を払う価値があるよね。