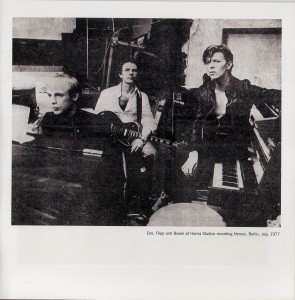批評性と言うコトバが今もかろうじて有効であるのなら、売文業として書き散らすにしろ極めて個人的な戯れとして論ずるにしろ読み手にそれとない微傷を残していくことこそ本懐とするべきではないだろうか。それは近年の主流になっているらしい、対象をネタとした自分語りや思い込みの正当化という定型性からの離脱であり同じく無意味な形容詞まみれの饒舌への倦厭でもある。まあそれも筆者が等身大の狂気かと見まごう領域まで踏み込んでいればそれはそれで面白いのだけれど。
てなワケで、8年前に書かれたであろう某アルバムについての海外レビューがあったとしたら。。。
Hollow Me/Yura Yura Teikoku (black to commm)
このゆらゆら帝国の新作「hollow me」は彼らを80年代によくあったVelvet UndergroundやCANの亜流、それも周回遅れの、と見くびっていた多くのリスナーを多少なりとも動揺させるに充分なものになりそうだ。
オープニングトラックからしてかつてのソリッドな、とげとげしい要素は注意深く去勢され、ギターソロの代わりにかつてのブラコンもかくや、という歯が疼くような間延びしたサックスが垂れ流される。
幾つかのトラックではギターはトレモロによってアタックを失い、リズムセクションには主体的、自律的な演奏は一切許されていない。「あえて抵抗しない」はSilver Applesへの遅すぎた謝辞のようであり「なんとなく夢を」はシングルヴァージョンにおけるDeluxe期のHarmoniaとPale Fountainsがトンネルの中で共演しているような鮮やかな翳りに代わってバスケットボールのドリブル音を思わせるドラムスのビートを枕に、よりジャジーな昼下がりの憂鬱の中へと耽溺してしまっている。
アルバム後半では緩やかなアブストラクト的傾向を見せ、Sweet SmokeやBrainticketといった70年代には失笑を買うことすらできなかったB級クラウトロックへの親和性を伺わせるが実験音楽やインダストリアルの陰惨さは微塵も感じられない。彼らの抽象はあくまで映像的かつ説明的であり個々の内奥をえぐり出すような心象描写やモンタージュまでには至らない。
「ひとりぼっちの人工衛星」は全体的にはTelexがカバーした「My Time」のヴァージョンをさらにメロウにしたような塩梅だが、Telexのセルロイドの透明な余情に比べるとはるかにウェットで感傷的だ。終盤出てくるアソウ・アイのLaurie Andersonばりのウィスパーは最後に定型ビートとのズレを生じさせることで夢見がちな楽曲と強引に距離を取っているようにも聴こえる。
ラストに配置されたタイトル・トラックはこれもアソウによる「Walkin On The Wild Side」から拝借したとおぼしきコーラスが、90年代には「フリーソウルのLou Reedってありますか?」とレコードを探しに来た若者が居た、という私の友人のレコード店主が語った嘘のような本当の話を思い出させる、ゆらゆら版フリーソウルだ。しかしかつての彼らなら慎重に施していただろう「Original Soundtrack」「How Dear You」ピリオドの10ccを想起させるアレンジのマニエリズムは失われており、ニューソウル的なコード進行に寄り添ったよりシンプルなメロディが強調されている。
全体的にはバンド性、つまり初期の彼らに感じられたtribe的な個々の緊密性は極めて希薄であり「しびれ」「めまい」以降、サカモトを中心としたプロジェクトとして製作された一連の作品としてはひとつの帰着を見たと言える。
このアルバムは母国の音楽、それも大衆的なものにしか親しんでこなかったリスナー層には少なからずインパクトを与えるだろう。そしてそれは無邪気なリスナーにとって知られざる宝探しの最初の一歩になるかもしれない。Velvetsの「Sunday Morning」が殺人を犯した翌朝の歌として密やかに語られて以来、ロックのもう一つの基本理念だった「虚無感」を、埃をかぶった屋根裏から今また日の当たる場所に引っ張り出してきてみせたコンセプチャル戦略も一定の成果を上げている。
しかしながらその「虚無感」もあくまで時代を覆っているのだろうあてどないメランコリアをモードとしてすくい上げディスプレイして見せたに過ぎず、決してその内実まで踏み込もうとはしない。「これから先が見たければどうぞご勝手に、ただし責任は取りませんよ」とでも言うように。
厳密に考えれば、ゆらゆら帝国がリアルにオリジナルな音楽性を志向していたのは4人編成だったごく初期だけだった。ノンエフェクトの2本のギターによる込み入ったアレンジメントとクリス・カトラー直系の硬質なドラムはMad Riverや初期QMSを思わせたが何より全体に張り詰めたヒリヒリとした皮膚感覚は他に類を見ないものだったからだ。
90年代の東京には「シブヤケイ」というムーブメントがあり、それらのバンドやアーティストがサンプリングしたり影響を受けたレコードが大量に売れたらしい。それらの作品はリスト化されファンの末端にまで行き届いたという。ゆらゆら帝国が参照しすくい上げたのは「シブヤケイ」のメインリストからこぼれ落ちたもの、クラウトロックや60~70年代サイケ、80年代のアンダーグラウンド音楽だったことは明白だ。かつての Sonic Youthがそうだったように。
(ただしゆらゆら帝国はフリージャズや現代音楽、コアなアヴァンギャルド音楽にまでは到達せず、自らもあくまでポピュラーミュージックの範疇から逸脱しなかった)
メジャーなミュージシャンによる墓暴きやタネ明かしは熱心な長年の探求者が多いこのジャンルでは決して歓迎されない。心血を注いで辿り着いた、ある種エソテリックなサークルの中でそっと耳打ちされ続けてきた音楽が、Led ZeppelinやPink Floydもほとんど聴いたことのない若者が最初に買う西洋音楽のレコードとして選ばれるのを苦々しく思う者がいるのは想像に難くない。
この音楽は多くのエピゴーネンを産むだろうが、同じものを参照したとしても彼らの中で何と何がどの感覚を拠り所にして繋がっているか、何故あるものはかすめ取れたのにもう一つのものには手を出さなかったのか、内実と剽窃とスタイルの微妙なバランス、それをモード的に纏めあげるには絶妙なセンスが必要となる。そしてその行為に対してあるべき後ろめたさのしるし、それはどこかに刻印されているのだろうか?