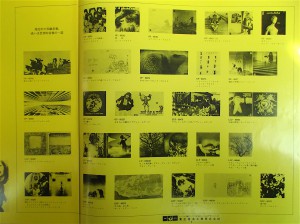88年、アムステルダム。初めて降りた中央駅は薄暗く、数人の浮浪者が道端に寝転がっているのか死んでいるのか。タクシーを拾うまでのわずかな時間に黒人を含む数人のプッシャーが「要らない?安くするから」と声をかけてくる。grassではない、snowだ。そういう目的で来たわけではないので丁重にお断りする。スイスからの列車のコンパートメントで隣り合わせた老夫婦に「アムスって危険だと言われてるけどそんなでもないよね?」ときくと、首を横に振って真顔で一言「dangerous…」と言われた時の感覚が蘇ってくる。急いでタクシーを拾い、予約してあるホテルの名前を告げた。
当時1UKポンドは300円以上、それに比べるとダッチ・ギルダーはものすごく安く感じた。老舗で底知れぬ在庫量を誇るレコードショップConcertoで面白そうなアルバムを何枚か見つけた後、無造作に床に置かれたバーゲン・ビンの箱にMark Glynne and Bart ZwierのHome ComfortのLPが何枚も打ち捨てられるように突っ込まれていた。この80年にアムステルダムで自主制作された(レーベル名がDivorced Recordsという..)アルバムは、大学時代、輸入盤店の新譜コーナーで見つけてから僕の中では特別な位置を占める作品だった。もちろん特段プレミアが付いているとかマニアが探しているとかそういうシロモノではなかったが日本円にして1枚数百円、信頼できる友達へのお土産としてそれらを買った。
それから10年ぐらい経って。知り合いだったアメリカのレコードディーラーの家に遊びに行き、朝食をとった後チェックしていたシングルの箱の中で初めて見るMark Glynne and Bart Zwierの7インチを見つけた。裏ジャケットに81年と記載、ということはアルバムの翌年だ。「how much?」「$10」高いな、と思ったが今後見つかる可能性も無さそうだし買うことにした。
東京に帰ってから早速針を落としてみるとアルバム冒頭の曲が、いかにも80年頃のポストパンクという風情にアレンジされたヴァージョンで収録されており面食らってしまった。A面のフェイドアウトがB面の頭にまで被ってしまっている。ジャケットデザインも投げやりだし、これはもはやこれまでだったのかと残念な気分になってしまった。
年を経て最近久しぶりにこのシングルを聴いてみたらこれはこれで終わりにしたかったのだろうな、と思えるようになっていた。別に僕が寛容になったわけではないけれど。
アルバムでは、意味深なフロントカバー写真、バックカバーにはアントニオーニの「夜」からのカットが流用され、長大な歌詞をびっしりプリントしたインサート、半切れになった”impriting is a curious form of early learning”の文字、曲のタイトル、レーベル名まで、彼らと他者との関係性をテーマとした透徹した美意識が感じられたがこのシングルでは全てが真逆に作られている。では彼らにとって「終わり」とはなんだったのか。
このHome Comfortのアルバムも決して名盤や推薦盤の類ではない。たまたま、80年、アムステルダムでひっそりと作られて、そして僕はそれを偶然同じ時代に受け取ってしまった、それだけのことだ。もちろん、すべての音盤はそのようにして存在している、と言ってしまえばそうなんだけど。